- トップページ
- 出版物・資料
- 資料
- 強震動地震学基礎講座
- 第8回:基盤と地盤特性の考え方
第8回:基盤と地盤特性の考え方Publications
地震波は震源断層で生成され、伝播経路や地盤の影響を受け地表面に到達する。図1はこのことを模式的に示している。
地震動の強さは、基本的に地震のマグニチュードと震源(央)距離の関数として記述できると考えられる。一方、過去の経験は、地震被害が地盤特性と密接な関係にあることを示している。関東地震の際、東京の下町では木造家屋の被害が大きかったが、山の手では土蔵の被害が大きかったことは、その典型的な例といえる。そこで、通常の地震動予測(設定)では、まず基本的な地震動を地震のマグニチュードと震源(央) 距離で設定し、次に地盤特性を別の方法で評価するという方法が採られる。
地震動が表層で著しく増幅されるのは、地下深部に比べて表層のS波速度(Vs)が 100~400m/sと遅いためである。そうした影響を受けない基盤面を考えれば、震源からの距離があまり違わない区域では入射波はどこでもほぼ一様と考えられる。この基盤を地震基盤と呼び、その設定条件は、
- 基盤面は空間的にある拡がりをもち、かつこの面での力学的諸性質は同一である。
- 基盤面以下の地層は、以浅の地層に比べて構成・力学的変化が一層小さい。
であることが、30年程前に提案された。
どの層を地震基盤とすべきかについては議論があるが、広い周期帯で考えるとき、どの地層が地震基盤として適当かは明らかである。図2は、東京の地盤を想定して計算された、地震基盤以浅の層によるS波の増幅率を示す。一点鎖線は土丹層(Vs=680m/s)、実線は地殻の上層(Vs=3km/s)、破線はマントルの上層(Vs=4.3km/s) を基盤とした場合である。この図は、工学上問題となる10数秒以下の周期領域においては、Vs=3km/sの層が地震基盤として最も妥当であることを示している。
一方、工学の立場からは、図1に示すように、地震基盤より浅部のVs=300~700m/s層に工学的基盤(工学的地震基盤)を設定するという考え方が提案されている。その主な根拠は、
- 工学的に最も重要な問題は、地盤の中に短周期成分が卓越するか長周期成分が卓越するかということではなく、地盤上に建設される構造物の固有周期に近い周期が地盤の中で励起されるかどうかである。したがって、基盤というものが地盤内で絶対的に決まるものではなく、同一地盤でも構造物の固有周期に応じて基盤が仮定されるべきである。
- 地震基盤は我が国の都市部では地下深部に存在しており、その深さでの観測例は少ない。これに対して、工学的基盤では多数の観測記録が存在するため、この深さで地震動を設定するのが現実的である。
- 関東平野・大阪平野・濃尾平野以外では(であっても)地震基盤までの地下構造に関する情報が少なく、地震基盤以浅の増幅特性を評価することが困難である。
というものである。
地震動予測(設定)という分野で基盤に対して二つの考え方が存在するのは、この分野が地震学と工学の境界領域に位置することに加え、工学分野の中でもそれぞれ異なった立場から学問が発達してきた歴史的結果といえる。今日では、構造物の長大化・高層化に伴い、周期10~20秒程度までのやや長周期地震動の重要性が認識されるようになったこともあり、地震基盤という言葉が地殻最上層のVs=3km/s層を指すという考え方は広く受け入れられるようになった。しかしながら、工学的基盤を定義し、そこでの地震動を設定することも広く行われている。地震基盤・工学的基盤と言葉を区別して使っていても、そこで地震動を設定し、それより上層の増幅特性を考慮するという思想は同じである。構造物の固有周期により、地震動の長周期成分と短周期成分で基盤の定義を変えるのは、工学の各分野における設計法の単純化という点で実務上の利点をもたらす半面、基盤での地震動特性や表層での増幅特性という概念について多くの見解が存在するという結果となっている。
現状の実務において、地震基盤・工学的基盤という概念に基づく強震動予測は多用されている。その代表的な例として、構造物設計のための入力地震動の設定や、自治体の地震防災計画のためのサイスミックマイクロゾネーション(一行政区画程度の広がりの地域に対して、地盤条件を考慮した地震動強さの分布、建物被害率の分布などを地図上に表現すること)への適用が挙げられる。それらの検討では、まず想定される地震の震源モデルや伝播経路の特性に基づき地震基盤における地震動を設定し、次に地震基盤以浅の地層構造に基づき地盤特性を評価することにより地表での地震動強さを求めるという方法が用いられる。本稿では、地震基盤や工学的基盤における地震動の設定法やそれぞれの基盤に対応した地盤特性の評価法にまで言及しないが、時代の進歩と個々の目的にあわせて、様々な方法が検討されていることだけを付け加えておく。表層地盤による地震波の増幅については、前号までの本講座に紹介されているので参照されたい。
本稿に関するさらに詳しい議論は、瀬尾和大(文部省自然災害特別研究成果報告書,地震活動と震害分布,20-24,1979)、入倉孝次郎(地震動と地盤,日本建築学会,93-101,1983)、工藤一嘉(宇津・他(編),地震の事典,325-336,1987)、纐纈一起(地震,第46巻,351-370,1993)を参照されたい。原稿に対し、山中浩明氏より貴重なご意見をいただいたことに感謝します。
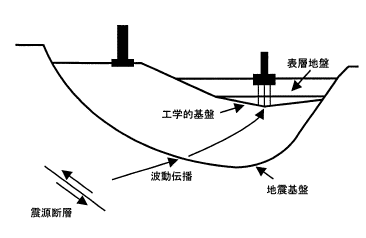
図1.地震波の伝播と基盤の概念
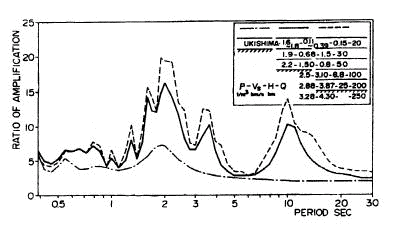
図2.基盤の扱い方による増幅率の差
瀬尾和大(文部省自然災害特別研究成果報告書,地震活動度と震害分布,p.20,1979)による。

