- トップページ
- 出版物・資料
- 資料
- 強震動地震学基礎講座
- 第3回:強震動予測で対象となる周期範囲
第3回:強震動予測で対象となる周期範囲Publications
構造物の設計や被害予測を行うために必要となる強震動を予測しようとする場合、考慮すべき周期範囲は対象となる構造物によって異なってくる。実際の構造物には揺れやすい周期(固有周期)と揺れ方(振動モード)がある。また、構造物が複雑になるほど多くの固有周期と振動モードを持つ。そして、構造物の地震応答を大きく左右するのが、地震動に含まれる周期成分の中でも特に固有周期近傍の成分である。ここでは、代表的な構造物(主に建築物)について、それらの地震応答に最も影響を与える水平方向(並進振動)の1次固有周期がどのような範囲にあるのかを中心にして述べながら、強震動予測で対象となる周期の全体範囲を、0.1秒から20秒までと論じている。
まず、我々にとってたいへん身近な存在である木造住宅についての固有周期を見てみよう。木造の固有周期は、平屋建てか二階建てか、新しいか古いかによって変わってくるが、ほぼ0.1秒から0.5秒までの範囲に分布している。平均的には、新しい二階建てが0.2秒前後、古い二階建てが0.3秒前後、平屋の場合はこれよりもやや短周期と考えれば良いだろう。二階建て木造住宅の中でも一階を店舗・二階を住居とする場合(店舗兼用住宅)においては、間口方向と奥行き方向とでは、剛性(変形に対する抵抗)に寄与する壁量が異なるため、固有周期にも差異が現われることもある。(間口方向の固有周期は奥行き方向のそれに比べて0.1秒から0.2秒程度長くなることがある。)ところで、1993年1月釧路沖地震以来、巨大地震が北海道を何度か襲ったが、この時、強震動が観測された割には被害が少ないことが指摘された。一般に寒冷地では開口部が少なく壁量が多くなる傾向があり、さらに北海道では落雪に配慮した鉄板葺きの屋根が用いられることや基礎がしっかりしていることなどから、耐震性が高かったことが一因とされている。このような木造住宅では、剛性も高くなり、固有周期は他の地域よりもかなり短いものと考えられる。
次も我々に馴染みの深い建物であるが、3階あるいは4階建ての一般的なRC造(鉄筋コンクリート造)の学校建物の固有周期はどのくらいだろうか。学校建物は長方形のプランを持つ単純な形状が多く、ほとんど同程度の固有周期を持つと考えられるが、実際には表層地盤の硬軟により変わってくる。硬い地盤上にある学校建物の固有周期は0.2秒程度であるが、これが柔らかい地盤上にある場合は0.3秒から0.4秒に伸びる。なお、学校建物の短辺方向と長辺方向のそれぞれの固有周期はほぼ同程度と考えて良い。また、学校建物のような水平方向に細長い形状の構造物は、その短辺方向において、並進振動の固有周期よりもやや短い周期に建物の長手方向の両端が逆に揺れるようなねじれ振動の固有周期が現われることもある。
続いて、より一般的な建物を考えてみよう。固有周期は建物の高さが高くなるほど長くなる傾向がある。1次固有周期T(秒)と建物高さH(m)の関係式として次式がある。
T=0.02H (S造)
T=0.015H(SRC造・RC造)
この式は日本における建築物を対象にしており、設計基準の異なる他国の建築物については式中の係数も幾分異なってくる。(なお、式中のS造、SRC造はそれぞれ鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造を意味する。)上式によれば、新宿副都心に立ち並ぶ200m 級の超高層建物(S造)の固有周期は約4秒と概算できるし、現在日本で最も高い横浜のランドマークタワー(高さ296mのS造)の固有周期は約6秒と概算できる。また、上式において建物の階高を3mから4mとすれば、1次固有周期と階数Nとの関係式として、
T=0.06N~0.08N (S造)
T=0.045N~0.06N (SRC造・RC造)
が得られる。また、高次の固有周期と建物高さの関係は、建物の特性(高さ方向の質量・剛性の分布など)により異なってくるが、特殊な形状の建物でなければ、上式で表わされる1次固有周期に対して、2次固有周期で1/3、3次固有周期で1/5と概算できる。(次いでながら、現在の建設技術によれば、高さ1000m級の超々高層建物の実現も可能であると言われている。
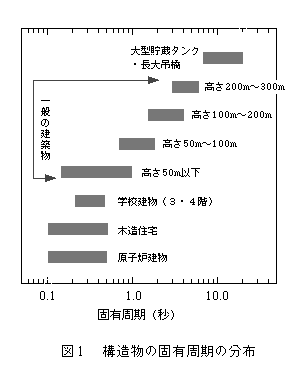 その固有周期は上式によれば約20秒に及ぶと推定されるが、これまでの超高層建物とは異なる構造形式の採用により10秒以下になるとも言われている。さらに、超々高層建物では地震動よりも風の影響が懸念されている。) 今度は、エネルギー施設を代表して、原子炉建物の固有周期について触れておこう。原子炉建物は、放射線や放射性物質の遮へいのために、RC造を採用し、壁厚1mを超える非常に剛な構造となっている。また、第三紀以前の岩盤に立地する。このため、幅、高さがともに60mから80mにも及ぶような巨大な構造物であるにもかかわらず、その1次固有周期は0.5秒以下となる。ここでは、現在の日本で多く採用されている原子炉建物の主なタイプであるPWR型(加圧水型)原子炉建物(以下、単にPWR型)とBW R型(沸騰水型)原子炉建物(以下、単にBWR型)についてそれぞれの固有周期を紹介しておく。PWR型は、硬い岩盤に立地し、同一基礎上に複数の建物が独立して立っている。代表的な振動モードとしては、外側の円筒形の壁とその頂部にドームを持つPC CV(プレストレストコンクリート製格納容器)の1次固有周期が約0.2秒にあり、内側の原子炉が設置されているI/C(内部コンクリート)が卓越して振動する1次固有周期が約0.1秒にある。一方、BWR型は、PWR型が立地する岩盤に比較して柔らかい岩盤に立地していることが多く、さらに建物全体が一つの強固な箱のような構造をしているため、その固有周期は地盤の硬軟による影響を大きく受ける。(ただし、岩盤の硬軟で原子炉の型を決めているわけではない。)その1次固有周期は0.2秒から0.5秒の範囲に分布する。
その固有周期は上式によれば約20秒に及ぶと推定されるが、これまでの超高層建物とは異なる構造形式の採用により10秒以下になるとも言われている。さらに、超々高層建物では地震動よりも風の影響が懸念されている。) 今度は、エネルギー施設を代表して、原子炉建物の固有周期について触れておこう。原子炉建物は、放射線や放射性物質の遮へいのために、RC造を採用し、壁厚1mを超える非常に剛な構造となっている。また、第三紀以前の岩盤に立地する。このため、幅、高さがともに60mから80mにも及ぶような巨大な構造物であるにもかかわらず、その1次固有周期は0.5秒以下となる。ここでは、現在の日本で多く採用されている原子炉建物の主なタイプであるPWR型(加圧水型)原子炉建物(以下、単にPWR型)とBW R型(沸騰水型)原子炉建物(以下、単にBWR型)についてそれぞれの固有周期を紹介しておく。PWR型は、硬い岩盤に立地し、同一基礎上に複数の建物が独立して立っている。代表的な振動モードとしては、外側の円筒形の壁とその頂部にドームを持つPC CV(プレストレストコンクリート製格納容器)の1次固有周期が約0.2秒にあり、内側の原子炉が設置されているI/C(内部コンクリート)が卓越して振動する1次固有周期が約0.1秒にある。一方、BWR型は、PWR型が立地する岩盤に比較して柔らかい岩盤に立地していることが多く、さらに建物全体が一つの強固な箱のような構造をしているため、その固有周期は地盤の硬軟による影響を大きく受ける。(ただし、岩盤の硬軟で原子炉の型を決めているわけではない。)その1次固有周期は0.2秒から0.5秒の範囲に分布する。
さてここで、強震動予測の対象となる周期範囲全体の下限と上限を考えてみよう。まず下限については、議論はあるだろうが、上述の構造物の固有周期をもとに0.1秒として良いだろう。一方、上限についての話をするためには、上述の構造物よりもさらに周期が長い構造物である石油やLNGなどの貯蔵タンクや長大吊橋の固有周期に触れておく必要がある。大型貯蔵タンクでは内容液がスロッシングする固有周期が20秒を超えるものが建設されている。また、明石海峡大橋やSan Francisco湾にかかるGol den Gate Bridgeでは固有周期はそれぞれ17秒、20秒に達するという。これら長周期構造物の存在により、上限については20秒として良いだろう。(図1を参照されたい。)
最後に、地震時の構造物の固有周期の長周期化について触れておく。地震動が強く構造物の地震応答が大きくなった場合、構造物の応答が弾性限界を超えて塑性化して剛性は低下する。その結果として固有周期が長くなる。この場合、構造物の地震応答に強い影響を与える地震動の周期範囲は、構造物の当初の固有周期近傍から、より長い周期範囲にまで広がってくる。1995年兵庫県南部地震においても、周期1秒のパルス的な波が膨大な被害をもたらしたが、大破した構造物の大半は周期1秒よりも短周期の構造物であった。従って、地震動予測において考慮すべき周期範囲は、まずは対象となる構造物の固有周期を含む範囲であり、さらに弾性限界を超えてからの損傷が懸念される構造物においてはより長周期側の範囲まで対象を広げなければならない。
著者の浅学により、土木構造物や免震構造物について述べることができなかったが、それらの固有周期も本稿で示した全体の周期範囲に含まれると考えられる。本拙稿により、強震動のどの周期範囲がどのような構造物に大きく影響を与えるのか、興味を抱いて頂ければ幸いである。

